【国税庁敗訴】が未上場株式の株価評価について、評価基準日を決算期末で評価してよいかどうかが争われた事例
- FLAP 税理士法人
- 7月28日
- 読了時間: 3分
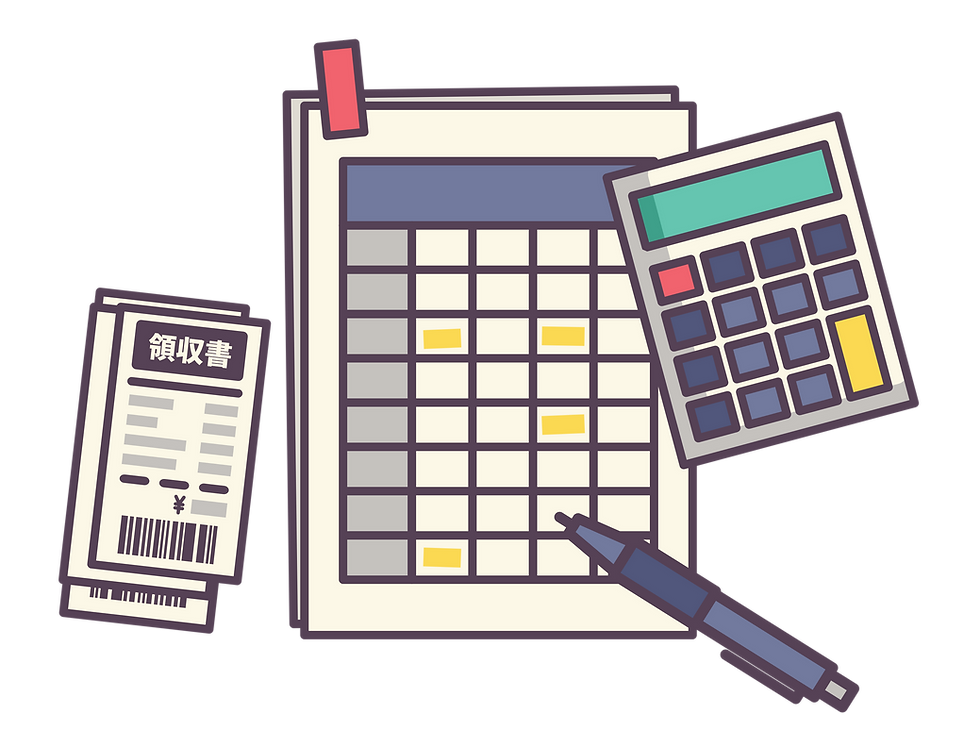
この裁決の要点
この事案は、納税者(請求人ら)が非上場株式を創業者一族から買い取った価格が「著しく低い価額」であったため、その株式の本来の価値(時価)との差額は贈与とみなされるとして、税務署(原処分庁)から贈与税の課税処分を受けたものです。
国税不服審判所(審判所)は、納税者と税務署のどちらの算定方法も誤りであると判断し、独自の計算に基づいて課税額を修正しました。その結果、贈与があったことは認めつつも、税務署が算定した贈与額よりは少ない金額とし、処分の一部を取り消しました。
事案の概要と各当事者の主張
当事者 | 主張 | 株式の評価額(1株あたり) |
納税者(請求人ら) | 売買価格は適正であり、「著しく低い価額」には当たらない。税務署の評価方法には誤りがある。 | 64,528円 |
税務署(原処分庁) | 売買価格は時価より著しく低く、その差額は贈与にあたる(相続税法第7条)。会社の資産・負債に大きな変動があったため、前期末のデータではなく、期末のデータで評価すべきだ。 | 278,200円 |
国税不服審判所 | 納税者・税務署、両者の評価額は共に誤り。正しい方法で再計算した結果、売買価格は時価より著しく低い。贈与は成立するが、税務署の計算した金額は過大である。 | 241,762円 |
審判所の判断の詳細
1. 株式評価の方法について
争点: 非上場株式の時価を算定する際、いつの時点の会社の財産状況を基準にすべきか。
原則的なルール(直前期末法): 株式の売買日(課税時期)と、その直前の事業年度終了日(直前期末)との間に、会社の資産や負債に「著しい増減」がなければ、計算を簡略化するために「直前期末」の財産状況で評価してよい、という通達(ルール)があります。
税務署の判断: 「著しい増減があった」と判断し、この簡略的なルール(直前期末法)は使えないと主張しました。
審判所の判断: 審判所が調査した結果、会社の資産・負債に「著しい増減はなかった」と認定しました。したがって、「直前期末法」で評価するのが妥当であると結論付けました。これにより、税務署の採用した評価方法は誤りであると判断されました。
2. 正しい時価の計算
審判所は、「直前期末法」に基づき、以下の点を考慮して株式の時価を再計算しました。
会社の資産に加えるべきもの: 帳簿に載っていなかった「損害賠償請求権」や「簿外資産」を資産として計上。
会社の負債に加えるべきもの: 「未払法人税等」や、売買日までに支払いが確定していた「配当金(1億1,000万円)」を負債として計上。
納税者はこれらの資産・負債を考慮せずに評価していたため、その主張する株価(64,528円)は不当に低いと判断されました。
この結果、審判所が算定した正しい1株あたりの時価は241,762円となりました。
3. 結論
審判所が認定した株式の時価総額: 60,440,500円
納税者が支払った売買価額: 16,132,000円
贈与とみなされた金額(差額): 44,308,500円
納税者が支払った金額は、審判所が認定した時価を大幅に下回っており、「著しく低い価額の対価」での譲渡に該当すると認められました。
したがって、税務署が行った課税処分自体は正しいものの、その算定した税額は過大であったため、処分の一部を取り消し、正しい贈与額(44,308,500円)に基づいて再計算すべき、という裁決を下しました。




コメント